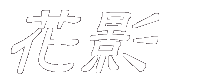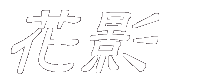f夕方、僕達は連れ立って出かけた。
研究所から、少し離れた山間。
世間から忘れ去られたような寂しい場所に、それはあった。
大きな桜の老木が数本、ひっそりと佇んでいる。
2週間ほど前、桜が開花し始めた頃、ようやく歩けるようになったばかりの彼女は
「夜桜を見てみたいの・・・。」と言った。
「ああ、いいよ。」
安請合いしてしまったが・・・
この辺りでは普通、開花から1週間で満開を迎えるのだが、今年は運いいのか(?)、開花から2,3日した頃から寒さがぶり返し、満開宣言がTVで流れたのは、一昨日の事だった。
今までの寒さが嘘のようになくなった日だ。
桜は一気に咲き進み、あっという間に散ってしまうかと思われたが、ここでもお天気の神様は僕達に味方してくれたようで、強い風が吹く事も、雨が降ることもなく、今日まで来た。
と言っても、桜の花が満開のまま僕らが見に行くのを待っていてくれるわけもなく、今は残念ながら、ちらりほらりと散り始めている状態だ。
満開の桜も美しいが、散り際の花吹雪が舞い散るさまもまた違った趣だ。
「風情がある」ってやつかな?
暖かいし、彼女の体調もここのところ順調なので
「これなら、夜桜見物もかまわんじゃろ」と
ギルモア博士の御墨付きが出たのが、今日の午前中。
午後の3時を過ぎた頃、僕達は研究所を出た。
「ゆっくり、見物しておいで。」
という、博士の言葉に甘えてちょっと早めの夕食を外でとり、ドライブしながら僕達は目的の場所に来た。
少し奥まったところにあるので、車を降りてからは、フランソワーズを抱きかかえてここまできた。
「恥かしいからいや・・・。」
そういう彼女を抱き上げた瞬間、以前よりも彼女は随分と軽くなってしまっていた事に気づいて、不覚にも涙が出そうになってしまった。
この数ヶ月間の記憶が蘇ってきた。
でも、そんなことはオクビにも出さずに
「大丈夫だよ。こんなところ誰も来やしないよ。」
僕はそう言った。
事実、ここに来る脇道に入ってからは、後続車はおろか、対向車すらこ来なかったし、人家からもだいぶ離れている。
「!!・・・・・」
それを目にした瞬間、彼女は言葉を失ったかのようだった。
街中に植えられている、ソメイヨシノの少しピンクがかった白とは違って、山桜との交配の結果であろう、ほぼ純白に近いその色は、満月の光に照らされて、とても神秘的に見える。
持って来たシートを敷くために、彼女を下ろすと彼女は、少し頼りなげな足取りで近くの樹に歩み寄った。
樹の幹に手を当て、その樹を見上げている。
「何をしているの?」
と問うと、
「こうしていると、その樹の精霊と話ができるんですって・・・」
と、見上げたまま答えた。
「ジェロニモ、かい?」
「ええ、彼がそう教えてくれたのよ。」
「で、君は、その樹の精霊と話せたのかい?」
「フフフ、私にはジェロニモのような力はないみたい。でも・・・」
「でも?」
「なんだか、とっても幸せな気分になれたわ。」
そう言って、彼女は微笑んだ。
シートに座った僕から、少し離れたその老木の傍らに立った彼女は白い月の光に照らされて まるで浮かび上がるように見える。
彼女の後ろに立つその老木の花は僅かな風にさえもはらはらと、その花びらを舞い踊らせる。
やおら履いてきた靴を脱ぎ捨てると、彼女は月の光と、桜の花吹雪の中で踊り始めた。
数週間前まで瀕死の状態だった、ほんの少し前まで歩く事さえままならなかった、そんな彼女と同一人物とは思えない程の、確かな、軽やかなステップで・・・。
だけど、そんな彼女の姿は舞台で見るそれとは違って、ひとまわりも、ふたまわりも小さくて、儚げで、あの頃よく見た悪夢の中の彼女の姿に見える。
「だめだ。」
彼女を力いっぱい抱きしめて、そう呟いた。
力いっぱい抱きしめて、そうして、彼女が僕から離れて行かないように。
僕を置いて行かないように。
彼女の髪の中に顔を埋めるようにして僕はまた呟く。
「僕を一人にしないで・・・。」
僕の腕の中で、彼女は一瞬躯を固くした。
僕は夢中で腕の中の彼女の唇を貪った。
今、解放(はな)すと、彼女が消えてしまいそうで、もう2度と戻ってこないようで、そんな畏れにも似た気持で、彼女をきつく抱きしめる。
華奢な彼女の躯が折れそうなくらいに・・・。
息苦しくなった彼女が顔をずらすと、今度は耳朶を甘噛みし、その白い首筋に唇を這わせ、わざと音を立てるように吸い上げ、僕の痕を刻みつける。
そう、彼女は僕のもの、誰にも渡しはしない。
「ぃや・・・・」
彼女の躯はもう力が抜けてしまっていて、樹に背中を預け、僕が片手で支えなければ立っていられない状態だった。
イヤイヤをするように首を振る彼女に構わず、残った片方の手で彼女の胸を露わにする。
月の光に浮かび上がる彼女の肌は透き通るように白い。
僕の目の前に曝け出された二つの乳房は、恥らうように、誘うように、微かに奮えている。
「きれいだ・・・。」
その谷間に顔を埋めると、彼女の甘い香りがする。
長いこと感じていなかった、僕だけが知っている彼女の香り。
僕は片方の乳房を揉みしだき、もう片方を頬ばった。
舌先でその先端を転がすと、それが自己主張を始める。
「あ・・あぁ・・・」
彼女の顔が少し歪み、甘い声が零れ出す。
僕だけが知っているその声を聞いて、僕の頭の中で僕の知らない僕の声がする。
「確カメルンダ、彼女ガ僕ノトコロニ、本当に帰ッテ来た事ヲ。彼女ガ今ココニ存在スル事実(コト)ヲ。
僕ダケノ、僕ニシカデキナイ方法デ・・・。僕ダケニ許サレタ手段デ・・・。」
僕はスカートをたくし上げ、彼女の泉を探る。
布越しにも判るほどに、そこは熱く湿っていた。
「あ・・・・・・ジョー・・・・」
彼女の躯が、ビクンと揺れ小さく撓る。
さっきまで白かった肌は少し上気したのか、ほんのりと桜色を帯びている。
もう、立っていられなくなった彼女を、さっき敷いたシートに横たえると、邪魔な布きれを取り去り、彼女の中に指を挿入(いれ)てみる。
「んんっっ・・・」
僕の動きに合わせるように、抗うように、彼女の躯は蠢く。
「や・・・」
「どうして?僕は、もっと君を感じたい。」
泉の少し上にある、小さな蕾に舌を這わせると、ほどなく彼女の躯は大きく弓なりに撓り、彼女の痙攣が伝わってきた。
「あぁ・・・」
一際大きな声をあげたかと思うと、彼女はガックリと脱力した。
「確カメルンダ・・・」
また、さっきの声が、頭の中に響く。
その声に従うかのように、僕は自分自身を、彼女の泉に押し当てる。もっともっと、彼女の体温(ぬくもり)を直に感じる為に・・・。
久しぶりのそこは、以前と同じで熱くて少し狭くて、そして心地よかった。
「やっと・・・また・・・、ひとつになれたんだね、僕達・・・。」
「ジョー、私・・・」
彼女の瞳にはうっすらと涙が浮かぶ。
「あ・・・」
僕が突き上げ始めると、目の前の乳房が揺れ彼女の吐息が再び漏れ出す。
僕は時折、彼女の胸に顔を埋め或いは首筋に唇を這わせ、その白い肌に、紅い花びらのような僕の痕を散らす。
「ジョー・・・。」
彼女が弾む呼吸の合間に僕を呼ぶ声が、一段と切なく甘く僕の耳を脳を刺激する。
物音一つしない静寂の中で、彼女の溜息にも似た甘い声と、僕らの肉体のぶつかり合う音だけが響く。
僕の頭の中には、最早、僕自身とそして彼女しか存在しなかった。
時間さえも止まったかのように感じた。
そして、突然に襲ってきた快感の奔流に抗うこともできぬままに押し流され、僕達二人は、ほとんど同時に意識を手放した。
どれくらい時間が経ったのだろう。
僕達は、繋がったそのままの状態で重なり合っていた。
月明かりに照らし出された彼女の白い顔を見ていると、この数ヶ月のことが、頭を過る。
ミッションの中、敵に撃たれ瀕死の彼女を抱きしめて呆然としていた自分。
ようやく連れ帰った研究所のメディカルルームで生命維持の為の機器類に囲まれ、体中にチューブやコードを固定され、時々苦しそうに顔を歪めていた彼女は、あまりにも痛々しくて、正視に堪えなかった。
彼女の呻き声を聞く度に、僕は自分を責めた。
なぜ、彼女を守る事が出来なかったのか?
何よりも大切な彼女一人も助ける事も出来ないなんて、最強と言われる僕のこの肉体(からだ)は一体何の為の存在なのか・・・。
彼女を守る為ならば、生命など惜しくはないのに。
何度も何度も、もうダメかと思った。もしそうなったら、彼女の亡骸を抱いたまま自分の生命を絶とうとも・・・。
彼女がいない世界には何の未練もないし、僕の存在する意味もなくなってしまうから・・・。
だけど、彼女はその度に奇跡を起こした。
ゆっくりと、だけど着実に死の淵から戻ってきた、僕の許へと・・・。
そして・・・そして・・・
「ジョー・・・どうしたの?」
彼女の細い指が、僕の目許を拭うように動く。
「フラン・・・」
喉の奥から、何か熱い塊のようなものがこみあげてきて、なかなか声にならない。
「フラン、やっと、本当に、僕のところに帰ってきてくれたんだね。」
彼女の柔らかな胸に顔を押しつけ僕はとうとう嗚咽を洩らす。
「もう二度と、僕を一人にしないで・・・」
「あなたを一人になんて、しない。
私はあなたの傍を離れない、離れられないもの・・・。」
そう言って、彼女は僕を抱きしめた・・・
その晩、僕は、久しぶりに夢を見た。
月の光に浮かび上がるような白い白い、君の姿
僕を見つめる君の蒼い瞳は、慈しむような優しさを湛えている
「フラン・・・」
僕は君の名を呼び、ありったけの力を込めて
君の細い躯を抱きしめる
君の躯の柔らかい感触
甘やかな、君の香り
僕を置いていかないで
僕を一人にしないで
いつでも、いつまでも、僕のそばにいて・・・
「大丈夫、あなたを置いてなんていかない。
あなたを一人になんてしない。
私は、あなたの傍から離れられないもの・・・。」
2003/6/16